こんにちは、わえ(@wae_lib)です!
 悩んでる人
悩んでる人NFTを勉強するのに『NFTの教科書』という本が気になる。実際に読んでみてどうだった?内容をざっくり教えてほしい!
このようなお悩みにお答えします。
- 記事執筆者:わえ(「わえのブログ」の運営者)
- 仮想通貨・ビットコイン投資歴4年
- ブログで仮想通貨・NFTに関する知識を発信
- Axie InfinityやSTEPNをはじめ、NFTゲームを複数プレイ
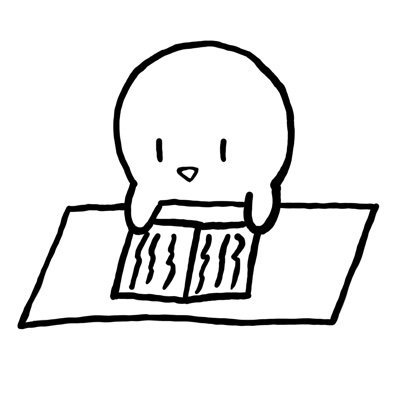
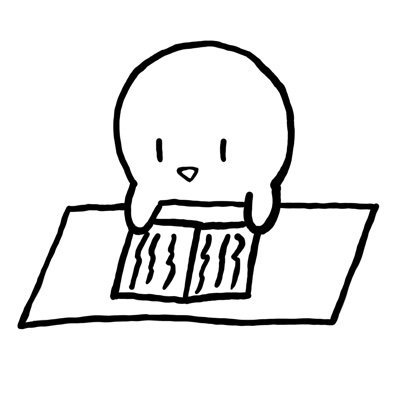
この記事では、NFTの売買をしていて、なおかつ年に200冊ほど本を読む本ブログ運営者のわえが、NFTに関する本である『NFTの教科書』の書評・要約をします。
「とりあえず早く買いたい!」という方は、以下のリンクからどうぞ。
また「NFTについて手っ取り早く知りたい!」という方は、以下の記事が参考になります。


本の著者はNFT分野のプロフェッショナルたち


『NFTの教科書』はNFT分野のオールスター28人によって、オムニバス形式で執筆されました。
NFTビジネスに携わっている方、NFTの法律や会計に詳しい方、NFTの未来を見据えている方、いろんな方々によって執筆されています。
編集者は天羽健介さんと増田雅史さん。
天羽健介さんはコインチェックに2018年に入社して、暗号資産(仮想通貨)やNFTの最前線で活躍されています。
増田雅史さんはスタンフォード大学ロースクールを卒業されていて、理系から弁護士になり、ITやデジタル関連の法的問題に精通されています。NFTやブロックチェーンに関する法的なアドバイスもされています。
このように『NFTの教科書』は、NFT黎明期にも関わらず多くの専門家たちを集めて執筆された、NFTの本です。
本の概要・要約
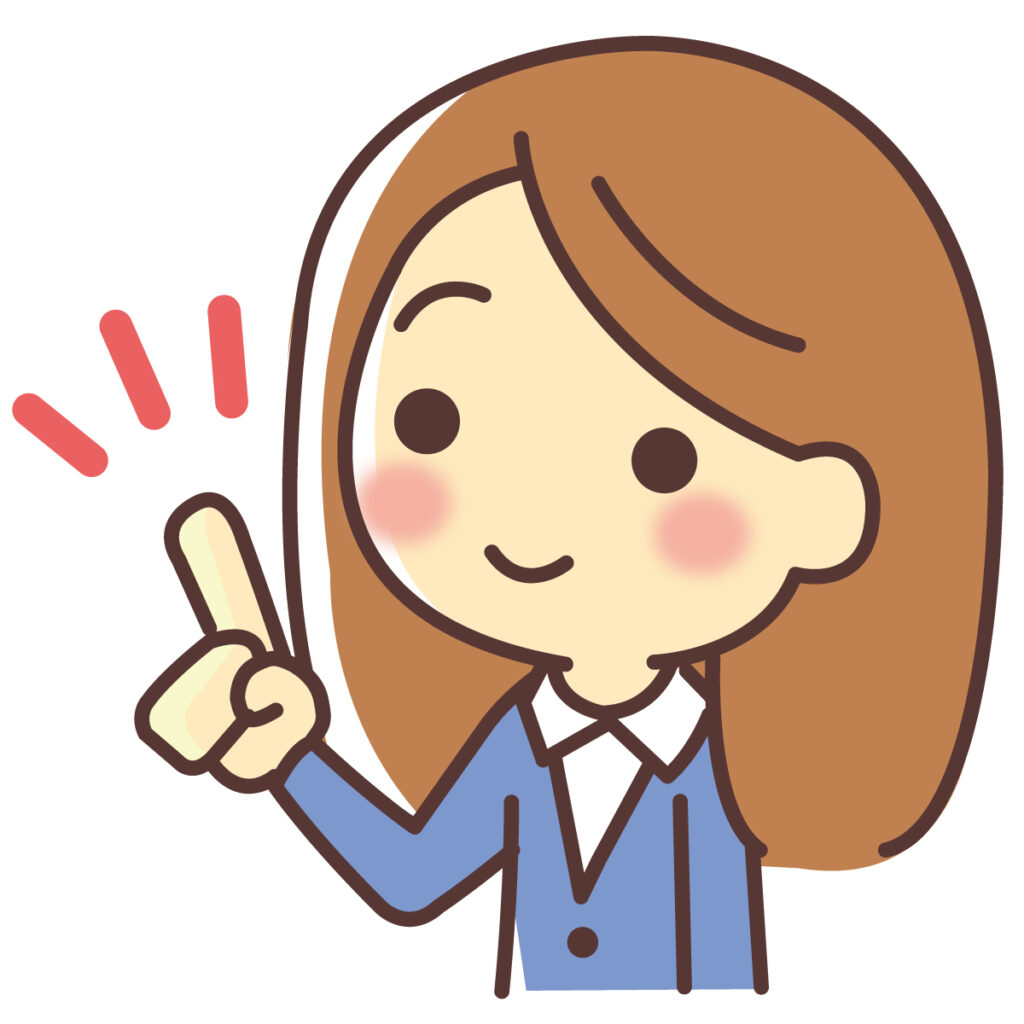
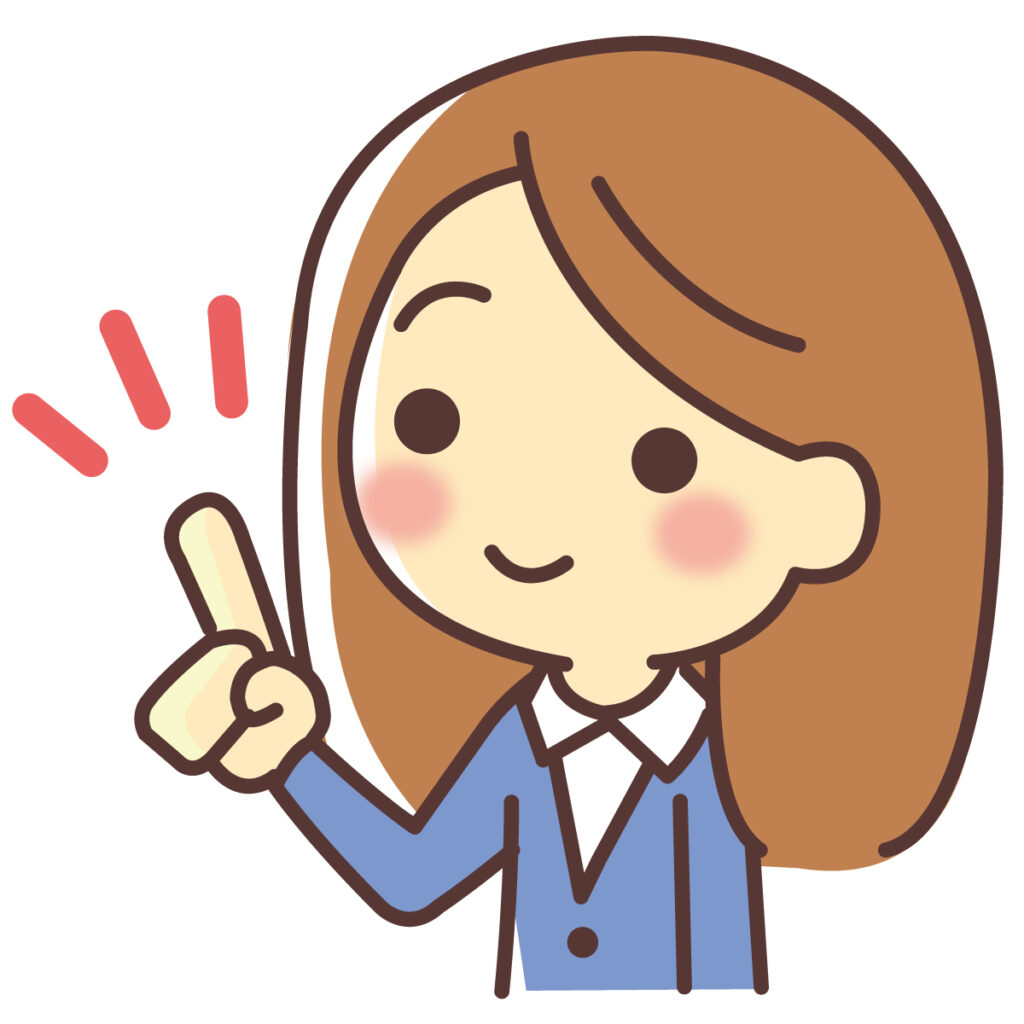
本書は大まかに以下の3章構成になっています。
- 第1章:NFTビジネスの全体像
- 第2章:NFTの法律と会計
- 第3章:NFTの未来
以下でそれぞれの章の概要・要約を見ていきましょう。
第1章:NFTビジネスの全体像
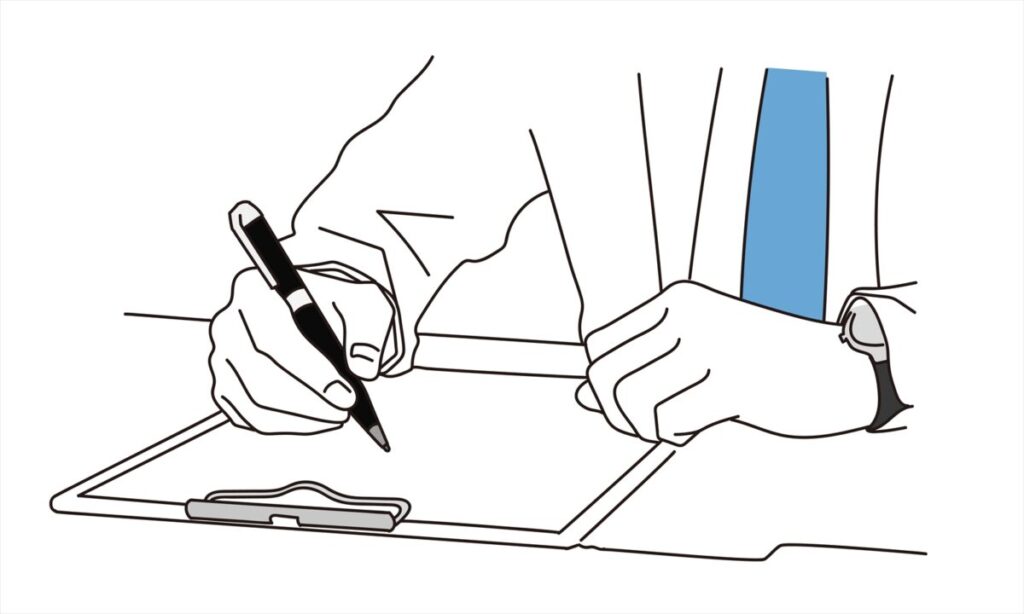
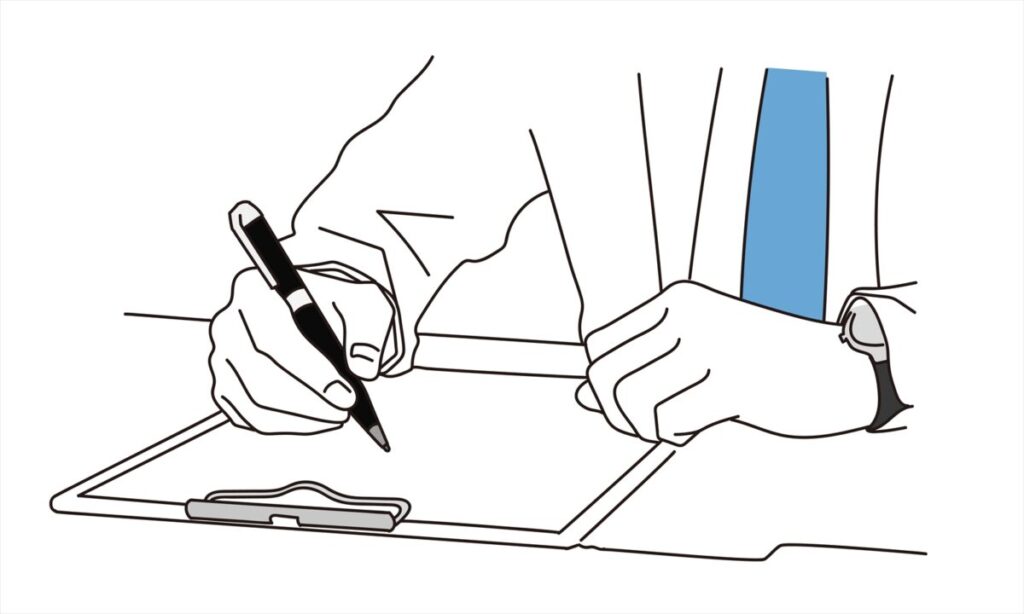
第1章では、なぜNFTが注目されているのかから始まり、NFTの主要なマーケットプレイスの紹介、NFTの様々なビジネス活用の紹介、NFTの技術的課題の提示がされています。
NFTが一般にどう利用されているのか、どうやったら自分もNFTを使えるようになるのか、じっくり読むことで勉強になる章となっていますね。
以下ではセクション別に内容を要約してます。
なぜNFTが注目されているか
NFTが注目されているのは、いくつかの大きなニュースが関係しています。大きなニュースとは、例えば以下のとおり。
- 2021年3月にデジタルアート作家のBeeple氏の作品「Everydays – The First 5000 Days」が約75億3000万円で落札された
- Twitterの共同創業者兼CEOのジャック・ドーシー氏の初ツイートが約3億1600万円で落札された
また、新型コロナウイルスの流行で会議などのデジタル化が進んだこと、次世代のSNSと言われるメタバースが注目されていることも関係しています。
メタバースの中では、モノの交換や売買にNFTが使われます。メタバースが普及すると、必然的にNFTの普及も進むでしょう。
2017年リリースのCryptoKittiesという世界初のブロックチェーンゲームが流行したこと、IP(知的財産)ビジネスとしての活用が可能であること、NFTを成長させるためのルール整備が整い始めていることも、NFT発展を後押ししています。
主要なマーケットプレイス
紹介されているマーケットプレイスは以下の9つ。
- OpenSea
- Rarible
- Foundation
- Binance NFT
- VIV3
- Atomic Market
- miime
- nanakusa
- Coincheck NFT(β版)
マーケットプレイスのそれぞれの特徴と、どんな人におすすめなのかが書かれています。
OpenSeaとCoincheck NFT(β版)での取引方法も紹介されているので、NFT売買をしたことがない人に参考になるでしょう。
NFTのビジネス活用の例
紹介されているビジネス活用例は以下の8つ。
- NFT×アート
- NFT×メタバース
- NFT×ゲーム
- NFT×スポーツ
- NFT×トレーディングカード
- NFT×ファッション
- NFT×音楽
- NFT×NFT特化型ブロックチェーン
本の中では、セクションを分けてそれぞれの活用例が紹介されています。
NFT×アートのセクションでは、CryptoPunks、HashmasksなどのNFTアートの例や、NFTアートの希少性、NFTを牽引するマーケットプレイスのOpenSeaとRaribleの成長について、国内のアート系NFTマーケットプレイスについて、NFTアートイベントや法規制についてなど、詳しく書かれていました。
NFT×メタバースのセクションでは、メタバースの定義、クローズドメタバースとオープンメタバース、メタバースでのNFTの活用事例(CryptoVoxels、Decentraland、Crypto Art Fes、The Sandboxなど)、CryptoPunksやBored Ape Yacht ClubといったコレクティブルNFTとメタバースの関係などについて書かれています。
NFT×ゲームでは、国内と海外にセクション分けがされています。
国内NFTゲームはMy Crypto HeroesやCryptoSpellsが紹介されていました。国内ゲーム業界がNFTの登場で今後どうなるのか、課題は何かといったことも書かれています。
海外NFTゲームでは主にThe Sandboxが取り上げられています。NFTゲームの世界的状況、ゲームとメタバースとの関係、ゲームにおける新しいビジネスモデルなどについて書かれていました。
NFT×スポーツのセクションでは、Dapper Labsによる「NBA Top Shot」というNFTコレクション例の紹介、代表的なスポーツNFT(Sorare、FiNANCiE、Chiliz)の紹介がされています。
NFTがより一層浸透するには、ユーザー教育とブランド力の強化が重要だということも記されていました。
NFT×トレーディングカードのセクションでは、代表例として「NBA Top Shot」、「2021 Topps Series 1 Baseball NFT」、Coinbook提供の「NFTトレカ」、BABYMETAL NFTトレーディングカードが紹介されていました。
NFT×ファッションのセクションでは、アート×ファッションのNFT、メタバース×ファッションのNFT、着せ替え×ファッションのNFT、リアル×ファッションのNFTが紹介されています。
Decentralandのアバターに着用させるNFTの話などが書かれていました。
NFT×音楽のセクションでは、NFT関連の取り組みをしているミュージシャンの例として、3LAU(ジャスティン・フラウ)、スヌープ・ドック、ダラス交響楽団、Perfume、GFRIEND、LOUDNESS、SEAMOが紹介されています。
音楽NFTサービスについても記述されていました。The NFT Records、テンセントミュージックエンターテイメント、JASRAC、OneOfといったサービスです。
NFT×NFT特化型ブロックチェーンのセクションは、海外発と国内発で分かれています。
海外発NFT特化型ブロックチェーンのセクションでは、NFTの技術として使われているL1インフラ(イーサリアムなど)とL2インフラ(Polygonなど)の解説がされています。
L2インフラはさらにChild Chain(Polygon初期)、Side Chain(Polygon、Roninなど)、Rollups(Immutable X)に分けられます。
国内発NFT特化型ブロックチェーンのセクションでは、Palette ChainやLINE Blockchainが紹介されてました。
NFTの技術的課題
NFT普及のために必要な4つの技術的課題は以下のとおり。
- NFT画像データの管理の問題
- トランザクションのスケーリングの問題
- NFTマーケットプレイス間の互換性の問題
- 環境問題への配慮
それぞれの解決法についても議論されています。
第2章:NFTの法律と会計
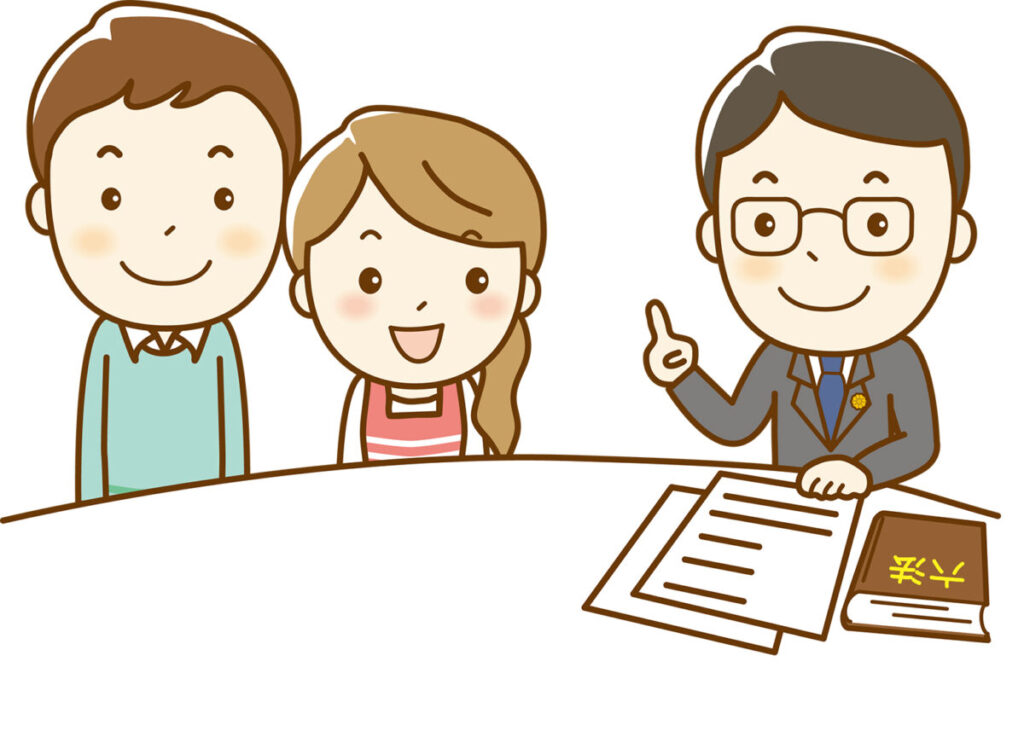
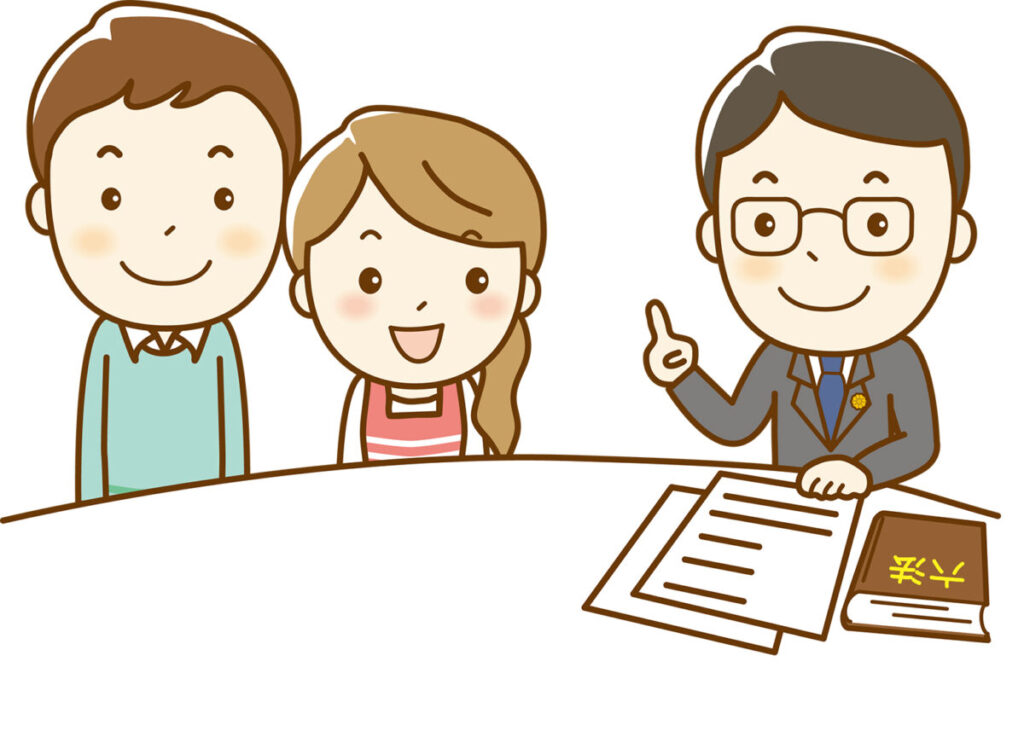
この章ではNFTの法律関係、NFTと金融規制、その他の法的諸問題、NFTの会計と税務について書かれています。
おそらく法律に詳しくない一般の方には、一読では難解な面も書かれています。
しかし、NFTと著作権の問題、著作権関連のケーススタディ、デジタルアートの「所有」の意味、NFTと賭博罪、NFTトークン発行者の販売時の会計処理、転売時の会計処理など、NFT売買をする方には関係してくる重要な内容も書かれていました。
これからガッツリとNFTの売買をする方は、何度も読み返して内容を理解したい章となっています。
第3章:NFTの未来


この章では、NFTの未来について論じられています。「NFTと無形資産」、「NFTと市場づくり」、「世界とNFT」、「NFTの展望」というセクション立てです。
「NFTと無形資産」のセクションでは、NFTが無形資産のイノベーションを起こし、世界経済の新たなトレンドを生み出す話が書かれています。日本でもNFTマーケットの拡大が期待され、注目したいところです。
「NFTと市場づくり」のセクションでは、デジタル資産市場づくりの先頭バッターに日本がなれるか、NFTは一過性のブームなのか、論じられます。
「世界とNFT」のセクションでは、香港を拠点とする、ブロックチェーン、NFT、ゲームの世界的先駆者のアニモカ・ブランズに焦点を当て、NFTの未来について記述されています。
「NFTの展望」のセクションでは、NFTをビジネスに生かすために重要なこと、NFTにしかできないこと、デジタルデータの資産価値について、NFTが生み出す新たな経済圏について、GameFiというビジネスモデルについて、資本主義のアップデートについて、書かれています。
NFTの未来を想像して期待を膨らませたい方、今後のNFTマーケット戦略を立てたい方などにオススメの章です。
本の書評・感想


わたしがこの本を購入したのは、ネットや他のKindle本でNFT関連の情報を漁っていて、基本的なことはわかったものの、「NFTについてもっと突っ込んで知りたい!」と思ったからでした。
ネットや他のKindle本には書いてない内容がかなり書いてあったので、この本を買って読んで結果的に良かったです。
「第1章:NFTビジネスの全体像」について
これまでわたしはNFT×アートの例ばかりしか知りませんでした。
しかし第1章でNFTのビジネス活用の例が網羅的に書かれていて、「こんな活用例もあったんだ!」と新たな発見ができました。
NFT×スポーツやNFT×ファッションは、一見「なんじゃそりゃ?」な印象を受けますが、内容を読んでみると、「ああそういうことか」と腑に落ちます。
NFT特化型ブロックチェーンの内容は少し難しい部分もありましたが、いろんなNFT用のブロックチェーンがあって、それぞれ役割が違うということが新たに分かりました。
NFTの技術的課題の話は勉強になります。将来的にこの本に書かれている課題が解決していくのか、見守っていきたいと思います。
「第2章:NFTの法律と会計」について
正直に言って、わたしはこの章は一読で全てはうまく理解することができませんでした。
ただ、次のことは理解しました。
- NFTには著作権の問題が絡んでいて、まだはっきりとした法律や規則が無く、ケースバイケースで問題を見ていく必要があること
- NFTと金融規制に関係があること
- ある種のNFTは賭博罪に抵触する可能性があること
- NFTに明確な会計基準はないこと
- NFTについて税法上に定義はないこと
今後NFT関連の法律や会計基準が決まったり変更したりすることで、この章の内容は刷新されるかもしれませんね。
少なくともNFTの売買をするときの著作権や賭博罪該当性には気をつけたいと思いました。
「第3章:NFTの未来」について
NFTは一過性のブームなのか、NFTはどのように世の中を変えていくのか、論じられている章ですね。
日本でも2021年にNFTが巷でブームになりましたが、今後更に日本でNFTが浸透するのかなど、ワクワクしながら読みました。
国内ですでに多くのユーザーを抱えるNFTマーケットプレイスがあるので、今後も続々と企業が参入するのではないか、NFTビジネスが活発になるのではないか、期待が膨らみます。
メタバースの普及が手伝って、メタバースでNFTを売買したり、メタバース内の経済圏ができたり、そういったことが当たり前になる未来も見えてきました。
NFTの登場により、全く新しい未来が来るのも近いかもしれませんね。
まとめ
最後までお読みいただき、ありがとうございます!
この記事では、『NFTの教科書』の書評・要約をしました。
NFTをこれから売買する人やNFTビジネスに関わる人はもちろん、NFTの法律・会計面を勉強したい人、NFTの未来を考えたい人にオススメの本です。
以下のリンクから購入できますので、買いたい方はどうぞご利用ください。
この記事があなたの参考になれば幸いです。






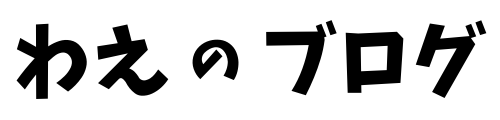
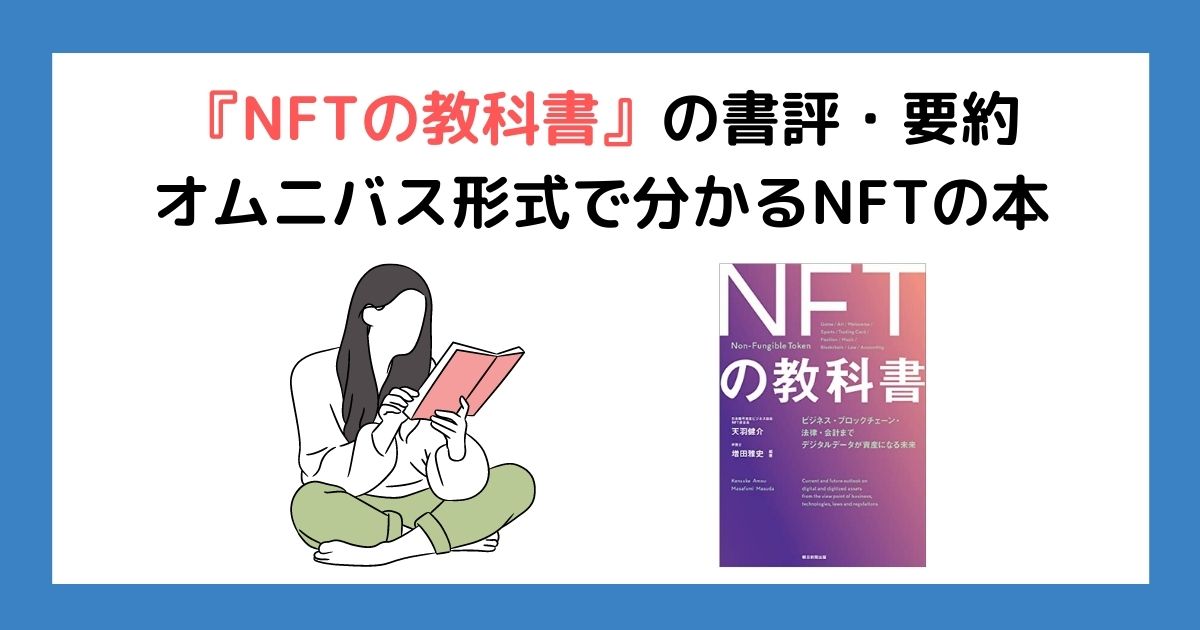

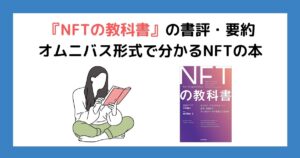
コメント