こんにちは、わえ(@wae_lib)です!
「人生について深く考えてみたい」
「哲学に興味があって、哲学関連の本を探している」
「偉人たちの思想に触れてみたい」
今回はこのような要望がある方向けに、私がこれまで読んだ中でもおすすめの哲学本を10冊、紹介します!
特に大学生・20代の方を対象と考えていますが、もちろんそれ以外の方にも役立つ書籍です!
史上最強の哲学入門
哲学初心者向けに、31人の哲学者についてわかりやすく紹介している書籍です。筆者の飲茶氏が『バキ』シリーズをリスペクトしており、『バキ』成分を本書に散りばめています。
私はこの本を読む前にニーチェの『ツァラトゥストラ』を読んで、「難しいなあ」と思い、この本を次の哲学本として読みました。
本書のニーチェの項で、『ツァラトゥストラ』では上手く理解できなかった内容を理解できました。超人と対比して末人(何も目指さずに生きている人間)があることを知りました。また、ニーチェは弱者を善とし強者を悪とする世に警鐘を鳴らしていたのだと、自分なりに解釈をしました。
初心者でも楽しく哲学を学びたい人に、最初の1冊としておすすめです。
史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち
上で紹介した『史上最強の哲学入門』と同じ筆者の飲茶氏の本で、東洋の哲人に絞った内容の本です。この本でも『バキ』成分が散りばめられています。
前作から引き続き、親しみやすい語り口調で説明がなされていて、読みやすく分かりやすいです。東洋哲学と西洋哲学の比較があって、世界の哲学についての理解が進みます。
学校で習った時にごちゃごちゃになっていた用語が、同じ概念を示していたことを知りました。例えば、無我、梵我一如、色即是空・空即是色、無為自然、悟り。
この本も初心者が楽しく哲学を学べる内容になっていて、入門書としておすすめです。
武器になる哲学
ビジネスマンが教養を高めるために、哲学に関する50個のトピックを学べる書籍です。哲学を、生活する上での知的な「武器」として学習したい方におすすめです。
本書が着目している点の一つは「個人的な有用性」で、それぞれの哲学者のアウトプットに着目するのではなく、アウトプットまでのプロセスに着目している点が類書との大きな違いになります。
たとえば、デカルトの「我思う、ゆえに我あり」そのもの自体はほとんど役立たないですが、その思考プロセスは有用だと本書は主張しています。
私はこの本を読んだ時点でいくつか哲学本を読んでいたのですが、今まで知らなかった目からウロコの思考に出会えました。特にナッシュ均衡の項の「繰り返し囚人のジレンマ」は面白かったです。
これからの「正義」の話をしよう
正義に関する哲学の本です。ベンサムやカント、ロールズ、アリストテレスなどの思想をもとに、政治や経済における正義について考察がされています。
私は以下の文章に感銘を受けました。
カントの言う尊敬は、人間性そのものへの尊敬であり、すべての人に平等に備わっている理性的な能力への尊敬だ。だから自分自身の人間性を侵害するのは、他者の人間性を侵害するのと同じように好ましくない。
『これからの「正義」の話をしよう ──いまを生き延びるための哲学』より
他者の人間性も自分自身の人間性も、共に大切だということが言語化されており、戒められた気持ちになりました。
現代における正義について哲学的な視点から思考を深めたい人におすすめです。
てつがくフレンズ
タイトル通り、女の子の姿になった哲学者たちが、哲学的な話をしながら学園生活を送る4コマ漫画です。漫画で楽しく哲学を学びたい人におすすめです。
想像していた以上にずっと深淵なストーリー展開でした。
前半では、主にソクラテスやプラトンを始めとする古代組の思想についてのエピソードがコミカルに描かれています。現代組が登場してきた後半からは、「人間とは何か」についてのシリアスなストーリー展開に移りました。
この展開にはドキドキさせられました。著者たちの創意工夫がいたるところに垣間見られます。続編をひそかに期待しています。
読書について
19世紀の哲学者であるショーペンハウアーが読書についての思想を語った書籍です。読書について思考を深めたい人におすすめです。
読書をすることについて、メリットばかりに目がいってしまいますが、この本では読書のデメリットを指摘しています。
多読することの弊害について語られています。「読書は自分で考えることの代わり」であるとし、読書ばかりしていると自分で考える能力が失われていく危険性を伝えています。
読書をする時は自分で考える習慣を忘れずに持っておきたいですね。
ライティングの哲学
哲学者の千葉雅也氏をはじめ、美学者・庭師の山内朋樹氏、読書家の読書猿氏、編集者・ディレクターの瀬下翔太氏が、対話形式で「書けない悩み」に関して哲学的に論じ合う本です。
執筆の「執」は、我執の「執」というのが印象的でした。ちゃんとしなければいけないという強迫観念から解放し、生産的にだらしなくなることを目指している点に共感します。
「他人に任せられるというのは、完璧を求めないことである」という千葉さんの話には、なるほどと膝を打ちました。一人で抱え込まずに、完璧でなくても他人に頼る。これぞ我執からの解放の極地なんだと解釈しました。
「書けない悩み」を持つ方が読めば得られるものがあるので、おすすめです。
その悩み、哲学者がすでに答えを出しています
「会社を辞めたいが辞められない」「嫌いな上司がいる」「人生が辛い」といった人類の共通の悩みに対し、哲学者たちはすでに答えを出していると、本書は語ります。
わたしは日々の悩みに対処する術を磨きたいと考えてこの本を読みました。古代メソポタミアの粘土板に日常の悩みや怒りが書かれていることを知り、太古の人々も現代人と似たような悩みを持っているんだなあと、共感を覚えました。
本書では、ドゥルーズの「資本主義からの逃走」、仏陀の「悩みを観察する人」、フーコーの「見えない他者」、アドラーの「課題の分離」、ショーペンハウアーの「孤独を愛する人」など、日常の悩みを解決するヒントとなる考え方が書かれています。
「人生の悩みが多いけどなかなか解決しない」という方が、解決策を発見するのにおすすめの本です。
君たちはどう生きるか
80年もの間読みつがれている、吉野源三郎氏の名著です。この新装版では、読みやすくするために現代仮名遣いで書かれています。
主人公のコペル君が母、叔父さんや友人たちを始めとする人たちと関わっていく内に成長していく物語です。小説形式で読みやすく引き込まれ、しかし内容は深遠。
貧困、いじめ、格差、勇気、学問といった、今も昔も変わらないテーマに対して、人としてどう向き合っていくか、考えさせられます。子供だけでなく、大人が読んでも参考になります。
「自分がどう生きるか」という問いに向き合いたい方はぜひ読んでみてくださいね。
方法序説
言わずとしれた、デカルトの有名な書です。初心者が1冊目に読むにしては難解なので、哲学書に少しなれてきた段階で読むと良いでしょう。
デカルトがどういった思考過程で「われ思う、ゆえにわれあり」といった普遍的思想にたどり着いたのかについて、徹底的に書かれています。
反宗教的な思想やアリストテレス=スコラ哲学の思想に反する思想への弾圧が激しかった中、「普遍的なものとなって後世に残るであろう、学問の方法、新しい科学や学問の基礎を示す広い意味での哲学の根本原理、自然の探求の展望と意味」(解説より引用)を著した本です。デカルトの学問への真摯な姿勢がひしひしと伝わってきます。
脱・哲学脱初心者を目指す方におすすめです。繰り返し読むことで、理解が深まることでしょう。
まとめ:哲学書を読んで壮大な思想に触れよう
最後までお読みいただき、ありがとうございます!
この記事では、大学生・20代の人におすすめしたい哲学書を10冊、紹介しました。
気になる本はありましたか?哲学という深淵な領域に踏み込んでみると、普段気づかないことに気付かさされることがあって面白いですよ。
あなたの読書生活に、少しでも役立てたなら幸いです!



安く読書したい!本を読む時間がない!という方へ
Kindleで本を選ぶ際、Amazonが提供している読み放題サービス「Kindle Unlimited」の対象商品を探すと得することがあります。月に2、3冊以上本を読む人で、「少しでも書籍代を安くしたい」「読みたい時に気軽に読み放題で本を読みたい」という方におすすめです。
最初の30日間は無料体験できます。
▶ Kindle Unlimitedの読み放題サービスを利用する
また、同じくAmazonが提供しているオーディオブックサービス「Audible」を利用することで、聴きながら本からの知識・情報を得ることができて便利です。「活字を読む時間がない」「ながら作業中に読書体験をしたい」という方におすすめです。
最初の1冊は無料で体験できます。
オーディオブックサービスには他にも、株式会社オトバンクの「audiobook.jp」があります。Amazonの「Audible」よりも料金が安く、オーディオブックを利用しつつ少しでも費用を抑えたい人におすすめです。
最初の14日間は無料でお試しできます。
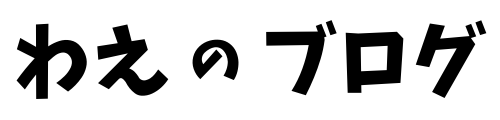
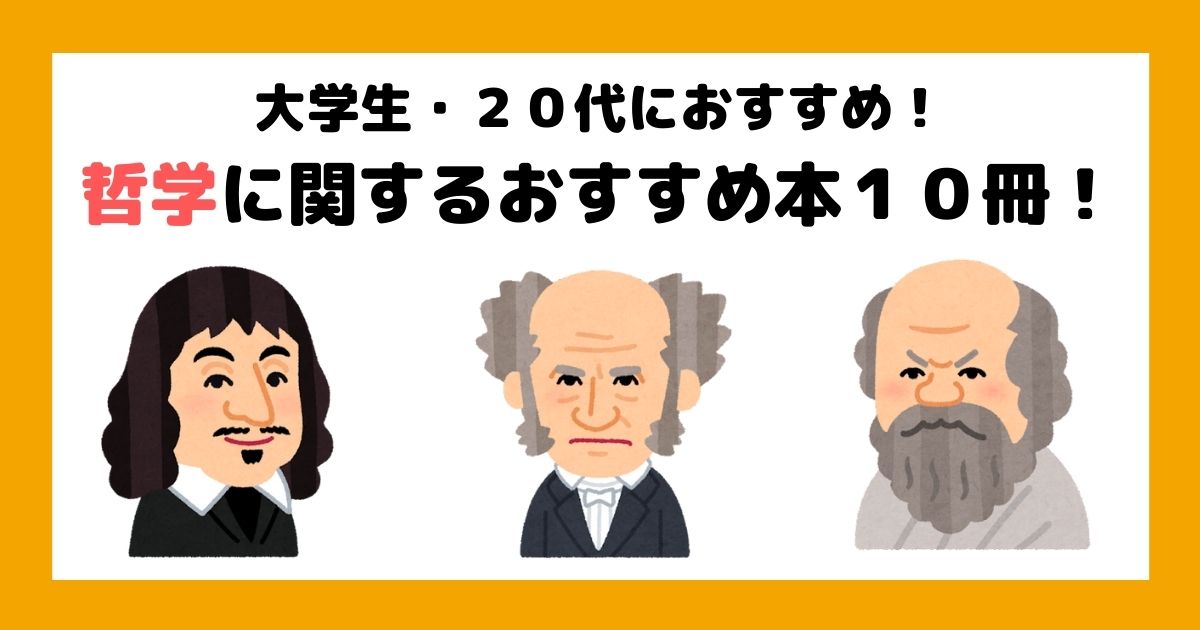










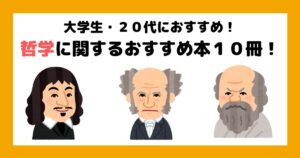
コメント